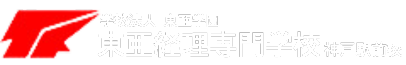Welcome to Toa Accounting Professional Training College

2級・第90回
和食の料理の味付けにおいて、「さしすせそ」という言葉をよく耳にします。これは調味料の頭文字をとって、語呂合わせにしたものです。「さ」は砂糖、「し」は塩、「す」は酢、「せ」はせうゆ(しょうゆ)、「そ」はみそのことを指します。和食の味付けは、基本的に「さしすせそ」の順とする説があります。甘味は食材にしみこみにくいため、砂糖は早めに入れます。先に塩やしょうゆを入れてしまうと、後で砂糖を入れても、甘味はつきにくくなるのです。また、塩を水に入れると浸透圧が高くなり、食材から水分を引き出すため、汁物の味をつける早めの段階に入れていきます。つぎに、「すせそ」の酢やしょうゆ、みそは、発酵調味料です。これらは熱を加えると味が変わってしまうため。後半に入れる場合が多いのです。特に酢は早め入れすぎると酸味がとんでしまうため、酸味が欲しいときは、入れるタイミングが重要です。また、しょうゆとみそは、香や風味を逃さないように、仕上げに入れることが望まれます。これらの調味料は、ただ単に味付けに使われているだけではありません。食材を柔らかくしたり、アクや臭みを取ったり、さまざまな役割も持っています。
| 文書の文字数(約) | 入力した文字数 | 入力した正解文字数 |
|---|---|---|
| 500文字 | 0文字 | 0文字 |
| 年・組 | 出席番号 | 氏名 | 文書の文字数(約) | 入力した文字数 | 入力した正解文字数 | 入力した分間 | 日付 |
|---|